| 特色ある取組〜国際交流による教育研究活性化〜 |
国際交流による院生の教育・研究意識の啓発
(交流協定校との国際共同セミナーの継続的・発展的開催) |
| (2) 取組の実施プロセス
|
①本取組を実施するに至った背景と動機
機械工学は全てのモノづくりに関わっており,社会の基盤技術の維持・発展に寄与している.近年,そのモノづくり系企業の経営や生産システムは,ますますグルーバル化が進んでおり,それら企業のニーズとして,研究や技術開発を行う上での国際交流経験(例えば,国際会議での発表や,外国人研究者との交流)を有する修士課程修了院生が強く望まれている.
一方,各専門領域の国際会議は,開催の約1年前にアブストラクトを添えた申込を行い,その後審査用のフルペーパーの提出と査読プロセスを経る.従って,研究の計画→先行調査→実験や解析等の実施→結果の検討・整理というプロセスを,2年間の課程内で行う修士課程院生が,国際会議において研究発表できる可能性は,通常極めて低い.実際,各専門領域の国際会議は,大学教員と企業研究者と博士後期課程(Dr)課程の院生の研究発表および議論の場となっている.
そこで,海外の学術交流協定校と本学機械工学専攻の共催で機械工学全般にわたる国際共同セミナーを独自に開催し,その場で修士課程院生全員に英語での研究発表の機会を与えることを考えるに至った.すなわち,学術的な進展を検討・吟味することを主目的とする通常の国際会議ではなく,あくまでも修士課程院生に対する教育的観点を第一として,達成された研究成果の高低に関わらず全員に国際共同セミナーでの発表機会を与える.学術交流協定校との共催のため,後述するように,開催する時期や方法を教育上効果的なものに設定できる利点がある.また,査読プロセスが無いため,申込から開催までの期間は2〜3ヶ月に短縮できるとともに,修士課程院生にとっても比較的容易に英語での研究発表が可能となる.
|
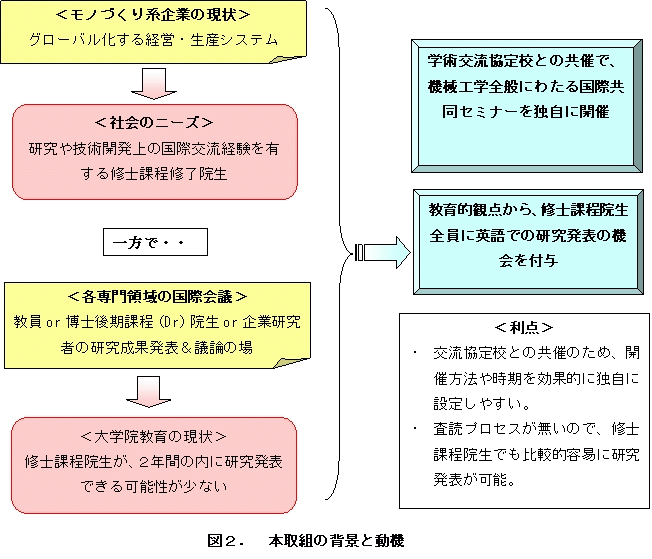
|
②本専攻教育課程での意義
- 本専攻カリキュラムにおいて,英語の発表や討論を行う外国人教員による科学技術英語の科目が3つ設けられているが,実際に外国人研究者と交流を行う場が無かった.本取組により,少なくとも2年間に1度は必ず口頭またはポスターによる研究発表を行う場が与えられ,貴重な国際交流経験を積むことができる.
- 現時点では,本国際共同セミナーで研究発表する修士課程院生に単位取得のメリットは無い.しかし,交流協定校の教員や院生と交流することで,院生の研究モーチベーションが向上し,様々な意味で研究活動の活性化に繋がっており,教育・研究上で極めて実効的である.
- 本取組は,機械工学専攻独自のものであり,学内あるいは学外に対して特色ある取組としてアピールできる.
|
③本取組のこれまでの経緯と問題解決
きっかけは,平成13年3月の釜慶大学校機械工学部と本学工学部の学術交流協定である.通常の学術交流協定では,窓口教員を中心に数名の教員の研究交流と,毎年数名の学生の交互留学が行われる程度である.当時の窓口教員を中心に検討し,より実質・実効的な学術交流協定にすることを目指して,当初は,国際共同研究推進を目的として第1回セミナー(開催地:釜慶大)を開催した.実際に本セミナーを契機として,釜慶大学と本学との間の国際共同研究が3テーマ実施されるに至った.
さらに,第2回セミナー(福井大学国際コングレス2002の一環)の際に,図3に示すように,本学機械工学専攻院生全員の研究発表(口頭またはポスター)を試行したところ,②で述べたような予想以上の効果があったことから,その後継続的に本取組を実施してきた.平成17年の第5回セミナーからは,新たに学術交流協定を結んだ上海理工大学も加わり,3大学による学術国際共同セミナーとして発展的に開催することとなった.
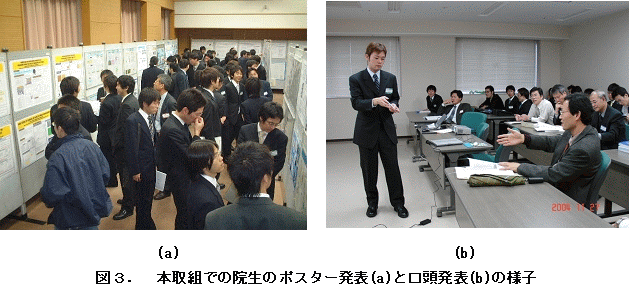 本取組の継続的な実施のためには,毎年の予算の確保と実務担当負担という大きな問題があった.予算とは,本学開催の場合は相手側教員・院生の国内旅費と宿泊費およびセミナー開催費であり,相手校開催の場合は本学教員・院生の海外渡航費が主である.実務担当負担とは,相手校との事前協議や予算獲得の申請,プログラム作成,論文集の発行,ホームページ作成等である.予算については,学内外の競争的予算の申請等により得た資金に加えて各教員の自己負担によりかろうじてまかなってきた.実務担当負担については,主に機械工学専攻の若手教員が継続的に負担してきた.
本取組の継続的な実施のためには,毎年の予算の確保と実務担当負担という大きな問題があった.予算とは,本学開催の場合は相手側教員・院生の国内旅費と宿泊費およびセミナー開催費であり,相手校開催の場合は本学教員・院生の海外渡航費が主である.実務担当負担とは,相手校との事前協議や予算獲得の申請,プログラム作成,論文集の発行,ホームページ作成等である.予算については,学内外の競争的予算の申請等により得た資金に加えて各教員の自己負担によりかろうじてまかなってきた.実務担当負担については,主に機械工学専攻の若手教員が継続的に負担してきた.
|

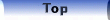
 |


