| 学習プラン(単位チェック表付) |
| 2. 履修科目と最低修得単位数 |
(1)履修科目(必修科目と選択科目)
すべての科目は,必修科目と選択科目に分けられます.必修科目は卒業するために必ず単位取得しなければなりません.一方,選択科目は,学生自身の判断によって履修する科目が選択できます(しかし,表2-2に記載される単位数を少なくとも取得しなければならないことに注意!).共通教育科目・専門基礎科目・専門科目のいずれも必修科目と選択科目に分けられています.共通教育科目では履修した科目を必修科目とするか否かを決めることが出来る場合もあります.
本学科の専門教育科目は,
●必修科目(表2-1に示すフローチャートの枠で囲んだ科目)
・・・・・将来,機械工学のどの分野を専攻する場合でも基礎として必ず修得すべき科目
●選択科目
・・・・・学生自身の判断により修得する科目を選択できる科目
(しかし表2-2に記される単位数を取得しなければならない)
に分けられており,学生がどのような分野に進んでも発展の原動力となる基礎的能力と専門性が得られるように配慮してあります.
|
(2)履修上の注意
共通教育科目,専門基礎科目,専門科目は,原則として追試験・再試験が行われないので,不合格となると再受講しなければなりません.したがって,不合格となった科目の時間枠で次年度の科目(必修科目であると大変!)を履修できなくなります.特に,単位を落としている学生は通年で開講される「機械工学実験」に注意して,受講計画を立てる必要があります.
なお,通常の講義は1コマが2単位ですが,実習,実験,演習は同じ時間数でも2単位とは異なりますので,学生便覧で単位数を確認して下さい.
|
表2-2 機械工学科卒論着手要件,卒業要件を満たす単位数
| 科目区分 |
開講単位数 |
卒論着手
要件 |
卒業要件 |
| 必修 |
選択 |
| 共通教育科目 |
大学入門セミナー |
|
|
|
2 |
| 基礎教育科目 |
外国語科目(英語) |
|
|
|
8 |
| 外国語科目(2外) |
|
|
|
4 |
| 保健体育科目 |
|
|
|
2 |
| 情報処理基礎科目 |
|
|
|
2 |
| 教養教育・副専攻科目 |
|
|
|
20 |
| 小 計 |
|
|
34 |
38 |
| 専門教育科目 |
専門基礎科目 |
22 |
14 |
|
|
| 専門科目 |
46 |
40 |
|
|
| 卒業論文 |
8 |
|
|
8 |
| 小 計 |
76 |
54 |
77 |
92 |
| 合 計 |
|
|
111 |
130 |
<履修要件>
その1. 卒業要件
次の要件イ,ロ,ハを併せて合計130単位以上を修得しなければ卒業できない.
イ.共通教育科目38単位
ロ.専門教育科目の必修科目76単位
ハ.専門教育科目の選択科目16単位以上
ただし,工学部他学科開講専門科目は,次の条件の下で専門教育科目の選択科目として
6単位までは卒業に必要な単位に算入できる.
a. 機械工学科の専門教育課程表にないこと.
b. 専門教育・副専攻科目として履修していないこと.
c. 担当教員の承認を得ること.
d . 同名の科目は1科目のみであること.
その2. 卒業研究着手要件
次のイ,ロを併せて合計111単位以上を修得しなければ卒業研究に着手できない.
イ.卒業に必要な共通教育科目38単位のうち34単位以上
ロ.専門教育科目77単位以上(3年次までの専門教育必修科目67単位を含む)
なお,上記その1. のただし書きは,卒業研究着手要件においても同様に適用する.
その3. その他
・教員免許のために開講されている科目の単位は卒業単位には算入しない.
・留学生対象科目は,留学生にのみ開講される.
|
|
(3)卒業論文着手要件と卒業要件を満たす単位数
4年次に卒業論文に着手することが認められる者は,「1年間で卒業に必要なすべての単位を修得見込みの者」に限られています.この判定は3年次終了時に行われ,表2-2の卒論着手要件に示す単位数を全て修得していることが必要です.卒業研究は1年間かけて行い,最後に研究成果を卒業論文にまとめます.
また,4年次を終了し大学を卒業するためには,表2-2の卒業要件に示す単位数を全て修得しなければなりません.表2-2に示す単位数は最低条件であるので,それを15〜30単位ほどは越える単位数を修得するように勉強することが望まれます.毎学期の終了時に,学務部教務・学生サービス課教務係や講義担当教員に問い合わせて,自分の修得できた科目と単位数を確認すべきです.
また,表2-3にある「専門科目の単位修得状況チェック表」を活用して,常に自分の単位修得状況を把握しておいて下さい.不幸にして,卒業論文着手要件,卒業要件の単位数を満たせない場合には,そこでいわゆる「留年」をすることになります.単位修得状況が著しく悪い場合には,退学を勧告されることがあります.
合格しなかった科目を再履修すると,それと同じ時間に開講される次年次の科目が受講できなくなり,必要単位がそろわなくなる恐れが生じるので,計画的に,しっかり勉強しなければなりません.
|
(4)卒業論文
3年次を終了し,卒業論文着手要件を満たした学生は4年次の1年間をかけて卒業論文の研究を行います.これは,それまでの授業が既知の理論や技術の体系をほとんど受け身的に学ぶだけであったのに対して,卒業論文は教員の指導のもとで時代の先端をゆく研究を行い,未知のことに挑んでゆくものです.あなたの斬新なアイデア,活発な行動力を発揮する1年となります.
専門分野に対応した「機能創成工学」講座,「熱流体システム」講座,「システム制御工学」講座のいずれかの研究室に所属して,そこでさらに深い専門の勉強をしながら,現象の解析や解明,実験装置の製作や実験,データの解析やシミュレーションなどを行って研究の仕方を学ぶと共に,自らの創意と工夫によって問題を解決する能力を養っていきます.
苦しい卒業論文の研究の1年間を講座の仲間と一緒に過ごすとき,研究ばかりでなく様々なプレイイベントが企画され,3年次までそれほど親しくなかった同級生とも遊び仲間として一生の親友になることがあります.また授業では聞き流していた指導教員の哲学を一対一で聴いたり,就職・進学を控えた仲間の本音の人生観が聞けることでしょう.「人と人のつながり」や「自分はどう生きていくか」をあらためて考えさせられる1年となるでしょう.
|

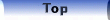
 |


