
| ■HOME / 講座・研究の紹介 / 熱流体システム講座 |
| 熱流体システム講座 Thermal and Fluid System Engineering | |
|---|---|
| 研究の紹介 | |
|
エネルギーは人類の生活を支え,経済社会の維持発展に必要不可欠なものです.熱流体システム講座はこのエネルギーに関する幅広い現象を教育・研究の対象としています.エネルギーは,エネルギー保存の法則が示すように発生も消滅もしないものですが,種々にそのかたちを変えながら環境や社会のなかを流れていきます. 多量のエネルギー資源消費が地球環境にさまざまな悪影響を及ぼすことから,エネルギー消費を抑制するとともに,利用価値のないエネルギーの排出量を地球環境の包容力の許す範囲に抑える必要があります.このためには,エネルギーのかたちを変換するときの効率を高め,人類にとって最終的に有効に活用できる量を増やし,さらに新しい利用方法を見いだすとともに,エネルギーの発生,消費,回収,排出について地球環境を含めたトータルシステムとしてとらえることが必要です. 以上のような観点にたって,熱流体システム講座では,大学院工学研究科,国際原子力工学研究所(敦賀)原子炉熱水力部門のグル−プと協力して,エネルギーの一形態である熱エネルギーの特質と移動,エネルギーを運ぶ媒体である流体とその流れの特質,熱・流体エネルギーを力学的エネルギーに変換する手法と変換機器および環境を含めた熱流体システムに関する講義を担当しています. 次に,各教員の研究内容を紹介します.
|
|
| 研究分野 | |
酒井 康行
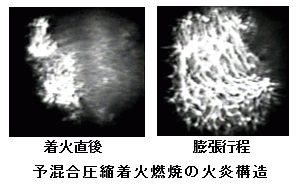 自動車技術は熟成され,進化の余地が小さい分野であるとというのは正しいのかもしれない.しかし,科学の世界では,分子レベルの設計,理論に基づいた情報の操作など目覚しい進化が起こっており,これらをタイムリーに取り込むことで進化を続けてきたのが自動車技術の歴史であったともいえる.将来の自動車技術のキーワードは自動車産業そのものの中にはなく,科学の世界や燃料・材料・加工・制御・情報などの周辺の最先端技術のなかにある. 当研究室では自動車用内燃機関の燃焼にターゲットを絞って研究を行っている.この20年の燃焼技術の成果はリーンバーンエンジン,直噴ガソリンエンジンという形で現れてきた.キーワードはそれぞれ,『乱れの制御』,『混合の制御』であった.今後の内燃機関の燃焼の進化を担うキーワードは『着火の制御』になるのではないかと考えている.一方で自動車用燃料源を見ると石油から天然ガスやバイオ燃料への転換が進んでいる.これらの燃料源から自動車用の液体燃料が作られる新しいインフラの出現の時期を利用すれば,さまざまな自動車用燃料を提案できるチャンスがある.
|
|
永井 二郎
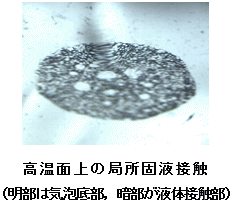 本研究室は,様々な『伝熱現象』を対象に,伝熱現象の解明や伝熱特性の制御に関する研究しています.例えば,地中熱や太陽熱といった自然エネルギーを利用した融雪・空調技術の開発や,新型ヒートパイプBACHの性能向上と実証へ向けた開発です.右図は,高温面に水が部分的に接触した時の瞬間写真です.このように高温面で固液接触部が発生する臨界条件を見出す基礎的研究も行っていますが,製鋼冷却プロセスの高度化等につながると期待しています. 研研究テーマの多くは企業等との共同研究や国からの研究助成課題です.大学院生と卒論生 あわせて10数名が,実験や数値解析を行い,喜びや苦しみをわかちあいながら研究生活を送っています.
|
|
田中 太
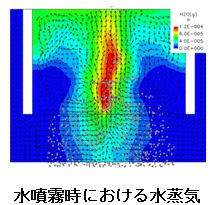 本研究室は,スプリンクラーなどの散水設備による火災抑制性能のモデリング,そして閉空間(トンネルや地下駐車場等)火災時における煙あるいはガス流動現象の解明を研究の柱としています.散水設備によって,火災を消し止められるか,あるいはどの程度の火災抑制効果が期待できるかなどを,工学的な方法で判定できるようにしたいと考えています.また,トンネルのような特殊閉空間火災では大量の有害な煙が発生し,人命救助や消火活動の障害になります.そこで,特殊閉空間における煙流動現象の把握や,どのようにして安全に排煙するかなどに着目して研究に取り組んでいます.本研究室では,火災実験と数値シミュレーションの両面から研究に取り組んでいます.
|
|
|
太田 淳一 環境やエネルギーに関する基礎的な現象には,液体と気体あるいは固体と液体の混ざって流れる混相流に関する物があります.これらでは興味深い現象が観察されます.それらの現象の応用を意識しつつ,可視化し,画像処理を用いて基礎的な研究しています.なお,当グループはいつも未解明な現象に魅せられて,一つずつ問題を解決しながら研究を進めています.最近のテーマは次です.
|
|
太田 貴士
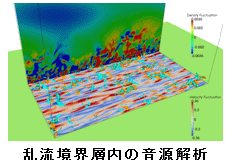 数値シミュレーションによって,安全性やエネルギー効率に関わる流体現象のメカニズムを解明し,各現象の予測と制御を実現するための研究に取り組んでいます.研究テーマの例を以下に示します.
|
|
望月弘保 (国際原子力工学研究所(敦賀) 原子炉熱水力部門)
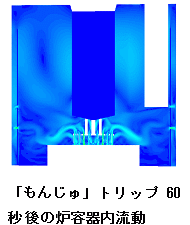 原子炉を含む熱輸送系や原子力プラントを構成する機器や系統の中で生じる様々な流動伝熱現象を対象にした次の様な研究を行っています.
|
|
